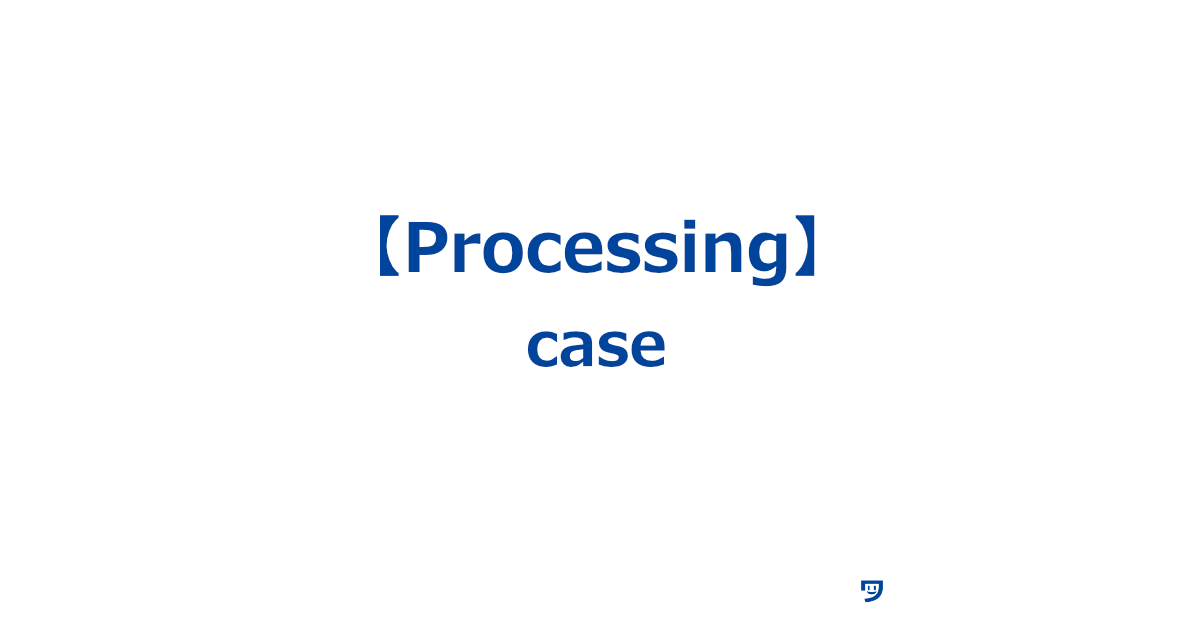ワタタク
ワタタク今回の記事の目的はProcessingの「case」を理解し、自分なりに使ってみること。
この記事を書いた人


上達の研究家 / アーティスト
「才能」ではなく「発見」で描く。文系・36歳からの上達ハック。
- ゼロから独学でクリエイティブコーディングに挑戦し、以下の実績を達成
- 開始1年8ヶ月目までに公募6つに挑戦し、3つ入選(勝率50%)
- KITTE大阪の18メートルあるAxCROSS大型スクリーン
- 虎ノ門ヒルズステーションタワーB2F TOKYO NODE エントランスサイネージで展示
- UN:O(東京大手町)にある会員限定のサテライトオフィスにて2作品常設展示
- 開始1年9ヶ月目に、虎ノ門ヒルズ49階、地上250mのインフィニティプールへ作品提供・展示
- 開始1年8ヶ月目までに公募6つに挑戦し、3つ入選(勝率50%)
- 【上達の秘密】
- 起源の物語:未経験から虎ノ門ヒルズ展示までの全記録(Genesis)
- 思考の技術:「上達」をシステム化する、モレスキン6冊の運用設計図
- ※虎ノ門ヒルズでの実績を出した「思考」と「経験」を、再現可能な形に体系化
目次
【Processing】caseについて
- caseの英語の意味は、英語で「場合」や「状況」
- Processingのcaseは、特定の条件に応じてプログラムの動きを変えるために使う
- 条件によって違う動きをさせたいときに役立つ
【Processing】caseの使い方【画像とコード】
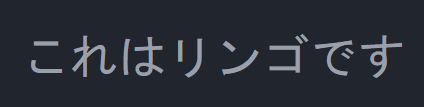
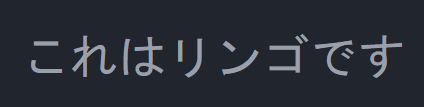
String fruit = "apple";
switch (fruit) {
case "apple":
println("これはリンゴです"); // fruitが"apple"の場合
break;
case "banana":
println("これはバナナです"); // fruitが"banana"の場合
break;
default:
println("これは知らない果物です"); // それ以外の場合
}【Processing】caseを使ってみた感想
1画面でいろんな表現をしたいときに、caseを使うと表現しやすそう。



それでは今日もレッツワクワクコーディング。