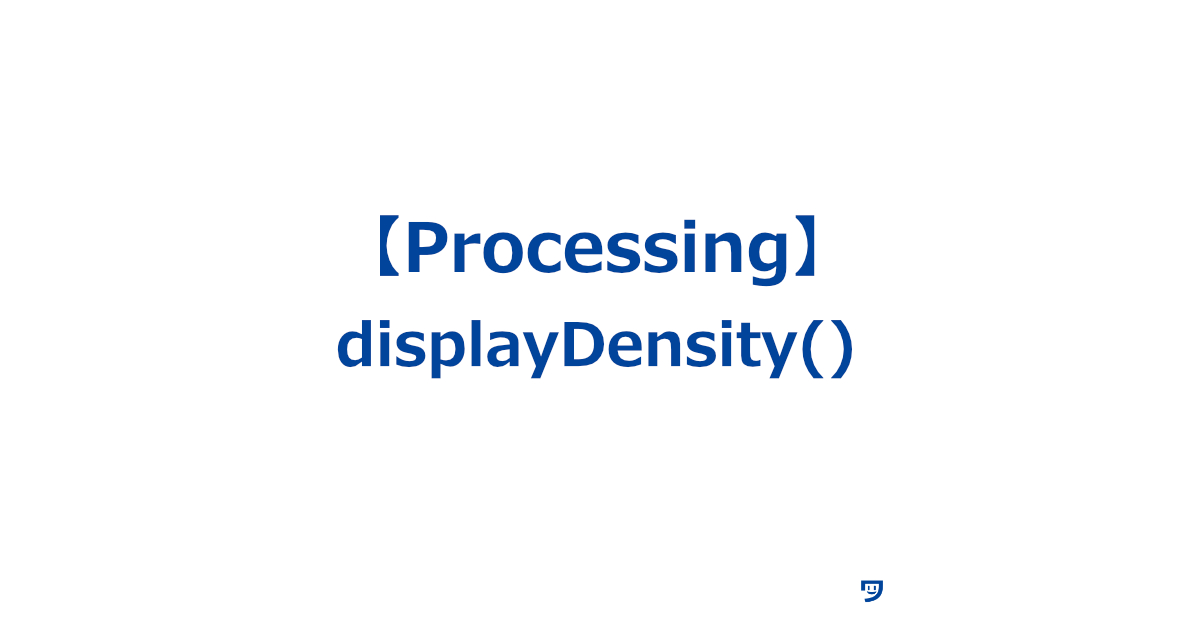ワタタク
ワタタク今回の記事の目的はProcessingの「displayDensity()」を理解し、自分なりに使ってみること。
この記事を書いた人


上達の研究家 / アーティスト
「才能」ではなく「発見」で描く。文系・36歳からの上達ハック。
- ゼロから独学でクリエイティブコーディングに挑戦し、以下の実績を達成
- 開始1年8ヶ月目までに公募6つに挑戦し、3つ入選(勝率50%)
- KITTE大阪の18メートルあるAxCROSS大型スクリーン
- 虎ノ門ヒルズステーションタワーB2F TOKYO NODE エントランスサイネージで展示
- UN:O(東京大手町)にある会員限定のサテライトオフィスにて2作品常設展示
- 開始1年9ヶ月目に、虎ノ門ヒルズ49階、地上250mのインフィニティプールへ作品提供・展示
- 開始1年8ヶ月目までに公募6つに挑戦し、3つ入選(勝率50%)
- 【上達の秘密】
- 起源の物語:未経験から虎ノ門ヒルズ展示までの全記録(Genesis)
- 思考の技術:「上達」をシステム化する、モレスキン6冊の運用設計図
- ※虎ノ門ヒルズでの実績を出した「思考」と「経験」を、再現可能な形に体系化
目次
【Processing】displayDensity()について
- 「display」とは「表示する」、「density」とは「密度」のこと。displayDensity()は「表示の密度を設定する」という意味
- displayDensity()関数は、プログラムが画面上に何かを表示するときに、その表示のきめ細かさを調整するために使います。例えば、タブレットやスマホなど、画面の解像度が異なるデバイスでの見え方を最適化する
- 【注意点】作成したイラストや作品が重くなる
【Processing】displayDensity()の使い方【画像とコード】
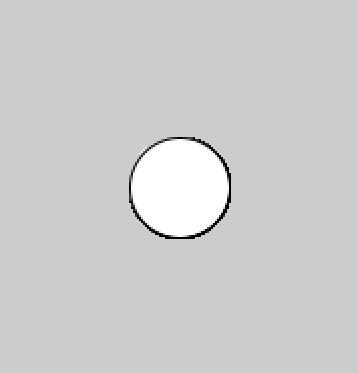
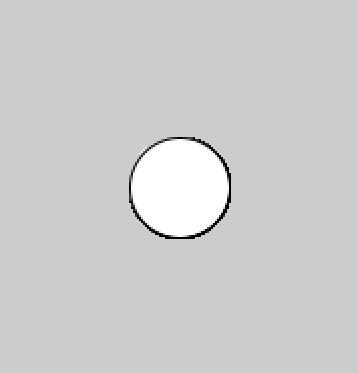
void setup() {
displayDensity(1); // 画面の密度を1に設定します(標準的な表示密度)
size(200, 200); // ウィンドウサイズを200x200ピクセルに設定します
}
void draw() {
ellipse(100, 100, 50, 50); // ウィンドウの中央に直径50ピクセルの円を描きます
}
【Processing】displayDensity()を使ってみた感想
タブレットとかスマホとかも使うときに、displayDensity()を思い出して使うことを考えてみる。



それでは今日もレッツワクワクコーディング。